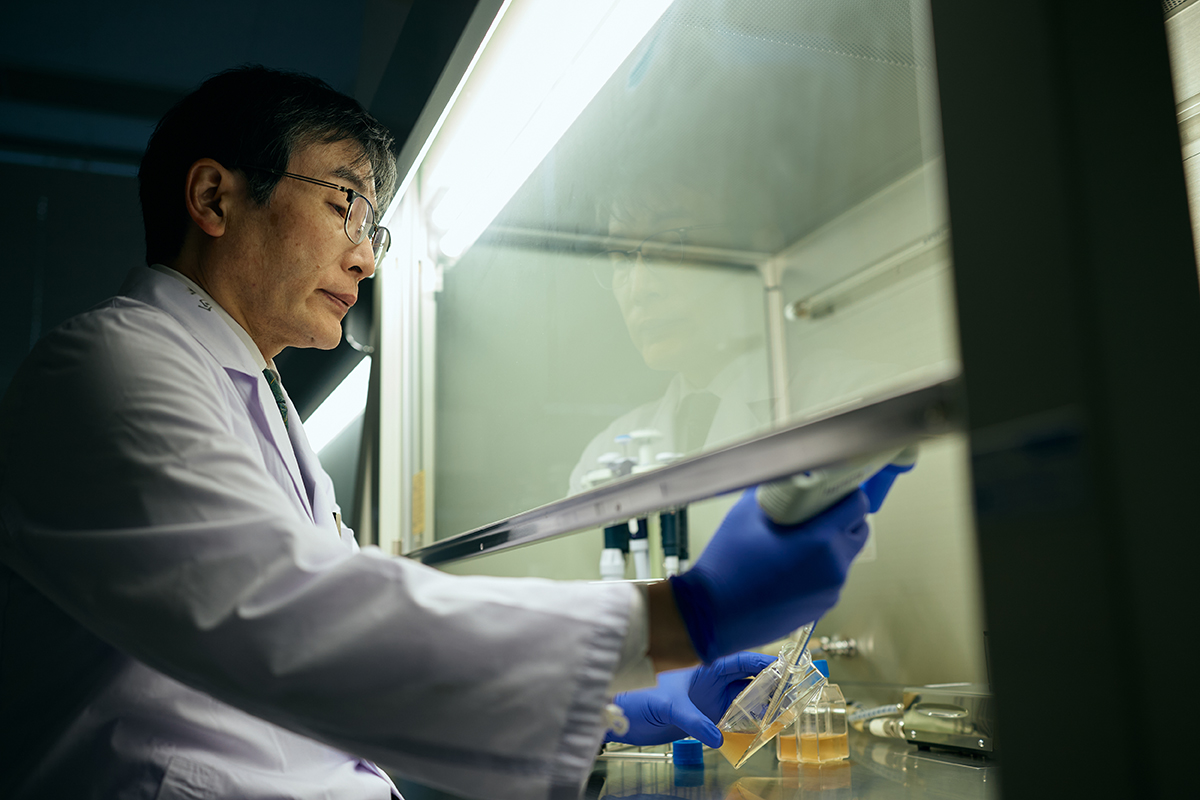研究内容
目の前にいる患者さんのために―。多発性骨髄腫の新たな検査・治療法を開発。
多発性骨髄腫は、白血病や悪性リンパ腫と同じ血液がんに分類され、血液細胞のひとつである形質細胞ががん化して骨髄腫細胞になることで発症します。研究者と臨床医の2つの顔を持つ髙松教授は、長年にわたって多発性骨髄腫の検査・治療法の開発に携わり、多くの患者さんに福音をもたらしています。
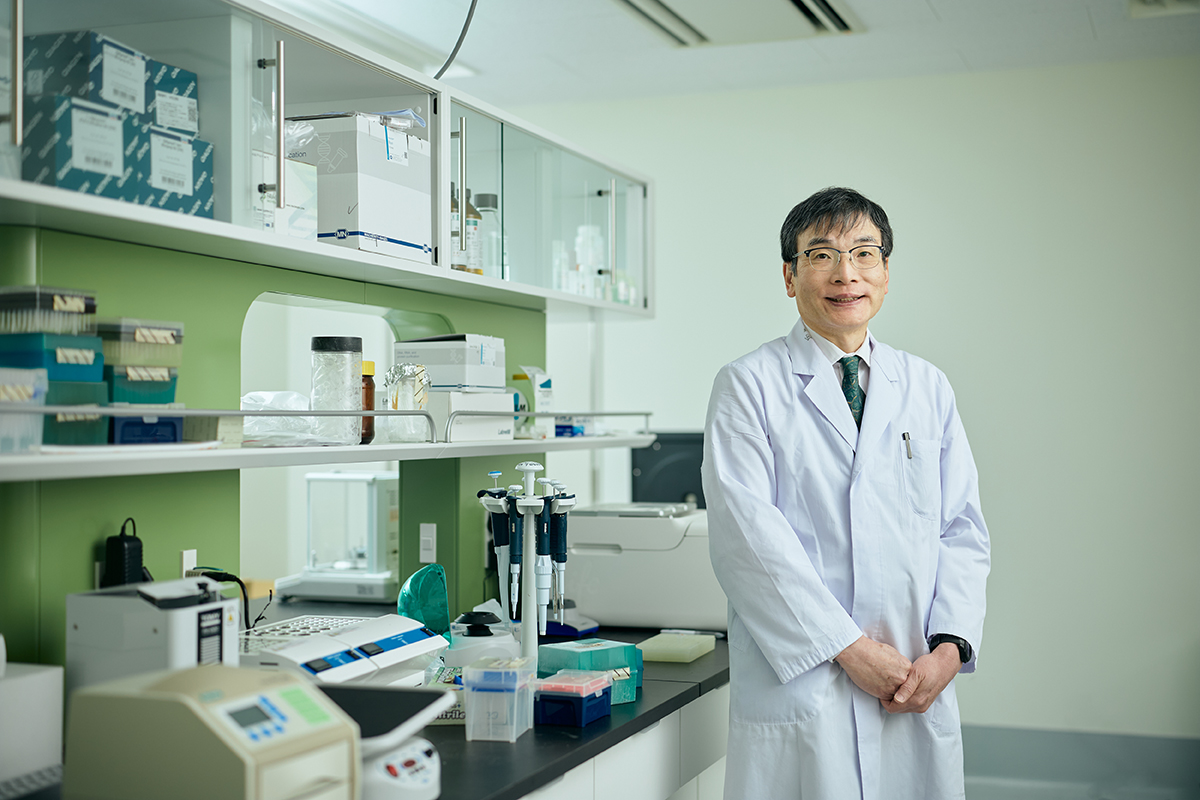
“治る”を確かめる検査
世界で初めて多発性骨髄腫の症例が報告されたのは1844年のことです。論文に掲載されたスケッチを見ると、患者さんの手足は折れ曲がり、骨は溶けてボロボロになっています。当時は不治の病でしたが、現在は治療法が目覚ましく進化し、一部の患者さんは完全に治ることが期待できるようになっています。
ただし予後予測、つまり治療の結果として治るのかどうかを調べるためには、腰の骨である腸骨に針を刺して骨髄液を採取し、非常に細かいレベルでがん細胞の有無を確かめる必要があります。
実際にどのような手法で検査を行っているのかというと、ひとつに、私が国内の臨床検査会社と共同で開発した検査法(フローサイトメトリー法)があります。蛍光標識した細胞にレーザーを当ててがん細胞を検出する手法で、保険適用され、日本全国で年間3000件程度実施されています。研究者として胸を張れる業績のひとつです。
このほか、次世代シーケンサー法と呼ばれる、DNAの配列を見て調べる検査法もあります。アメリカで承認されている検査法で1750ドルと高額ですが、白血球100万個に1個の腫瘍細胞を検出でき、非常に高感度です。
ただこれらの検査法はいずれも検体が骨髄であり、患者さんに骨髄採取という大きな負担を強いることになります。
「採血」でできる検査を開発
私が今、臨床導入に取り組んでいるのは、血液(血清)を検体としてがん細胞の残存を評価する質量分析法です。がん細胞が分泌する微量のたんぱく質を測定するもので、感度は次世代シーケンサー法と同等かそれ以上です。コストは1000ドルと高額ですが、採血ですむので、患者さんの身体への負担はありません。
私は質量分析法は、多発性骨髄腫が治ったという指標、すなわち治療をやめられるという指標になると考えています。多発性骨髄腫の治療は高額となることが多く、医療保険財政を圧迫しています。検査により高額の治療をやめられることが分かるのであれば、保険適用への道が開けます。
さらに、たんぱく質の代わりに、がん細胞の表面に発現する抗原を検出する検査法の開発にも取り組んでいます。血清を検体とし、質量分析装置を用いないため1検体あたり1000円と非常に安く検査ができ、今後の研究次第で、質量分析法と同じくらいの感度が出ると期待しています。
CAR-T細胞を作製、新たな免疫療法を開発
検査法だけでなく治療法の開発も進めています。
血液がんの新たな治療法として注目を集めている「CAR-T細胞療法」をご存知でしょうか。患者さん自身の免疫細胞を取り出し、遺伝子改変を行って(CAR-T細胞)体内に戻し、がんに特異な抗原を標的としてがん細胞を攻撃させる治療法です。日本でも承認されており、3300万円という高額な治療費がかかりますが、1回の投与で約20%が治ることが期待されています。一方で、CAR-T細胞療法を行った後にがんが再発した場合は、標的となる抗原が消失し、がん細胞がCAR-T細胞の攻撃から逃れるケースがあります。
私が現在取り組んでいるのは、HLA-DPという抗原を標的とするCAR-T細胞の開発です。HLA-DPは血液の細胞に幅広く発現する抗原なので、さまざまな血液がんに効く可能性があります。同時に、血液以外のほとんどの細胞には発現しないため、副作用があまり出ません。すでにマウスを使った実験で、新たに作製したCAR-T細胞は、既存のCAR-T細胞と同等の治療効果を発揮することを明らかにしています。

患者さんに希望を
大学の研究室と附属病院の臨床現場を行き来しながら、研究を進めています。学位を取得した論文は再生不良性貧血がテーマでしたが、医師として血液がんの患者さんと接することが多く、「目の前で困っている人のため」にという思いで分野を変えた経緯があります。
医学の発展はめざましく、今は治らないと言われる病気も数年後には治る可能性があります。患者さんに希望を届けたいという思いが、研究のモチベーションとなっています。